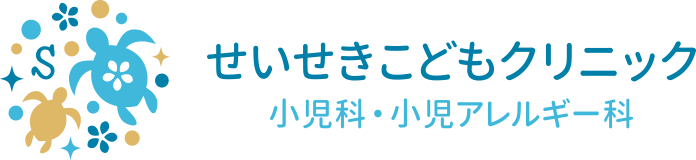目次
初めて赤ちゃんが熱を出すと、パパやママはとても心配になりますよね。赤ちゃんの発熱は成長の過程でよくあることで、体が病気と戦っているサインでもあります。大切なのは、正しい知識を持って落ち着いて対処すること。この記事では赤ちゃんが発熱する主な原因や、おうちでできるケア方法、そして**「どのタイミングで病院に行けばいいのか」**といった受診の目安について分かりやすくご紹介します。情報提供と同時に、「大丈夫、きっと乗り切れる」という安心感もお届けできれば幸いです。
なぜ赤ちゃんは熱を出すの?~発熱の主な原因~
まずは「発熱」という体の反応について知りましょう。発熱はウイルスや細菌に対する防御反応の一つであり、体温を上げることで病原体の活動を抑えようとしています。赤ちゃんは大人より平熱が高めですが、一般に体温が37.5℃以上あると発熱と考えます。では、どんな理由で赤ちゃんは熱を出すのでしょうか?主な原因を以下にまとめました。
感染症によるもの
風邪などウイルスや細菌の感染が最も一般的な原因です。赤ちゃんの免疫システムは未熟なため、病原体と戦う過程で熱が出ることがあります。発熱自体は体が病気と戦っている証拠なので心配しすぎないでくださいね。
予防接種後の発熱
ワクチン接種の後、体が免疫を作る反応として一時的に熱が上がることがあります。通常は半日~1日程度で落ち着く軽い発熱なので、機嫌が良ければ様子を見ても大丈夫です。
歯が生える時期
生後6か月頃から乳歯が生え始めますが、そのタイミングで軽い発熱をする赤ちゃんもいます。高熱になることはまれで、これも成長の一環と言えます。機嫌が良ければ特別な心配はいりません。
厚着・環境要因
着せすぎや室温の上げすぎでも一時的に体温が上がることがあります。特に冬場に心配で厚着させすぎたり、暖房が効きすぎたりすると赤ちゃんは体温調節がうまくできません。熱っぽいと感じたら服装や室温をチェックしましょう。(※後述の対処法で詳しく解説します)
以上のように、発熱の背景にはさまざまな原因があります。発熱そのものは悪いことではなく、多くの場合「体ががんばっている」サインです。原因を踏まえつつ、次章では実際に熱が出たときのお世話のポイントを見ていきましょう。
赤ちゃんの発熱時のホームケア5つのポイント
赤ちゃんが熱を出したとき、おうちでどのようにお世話をすれば良いでしょうか?基本的な対処の流れを5つのステップにまとめました。順番に落ち着いて対応してみてくださいね。
-
まず体温を正確に測ろう: 熱いと感じても実際に体温計で測ることが大事です。赤ちゃんの場合、脇の下にデジタル体温計を入れて測定するのがおすすめです。一般的に37.5℃以上あれば発熱と判断します。測定時に動いて誤差が出やすいので、しっかり脇に体温計を挟んで測りましょう。なお、衣類の着せすぎや布団のかけすぎで一時的に体温が上がっていることもあります。厚着かな?と感じたら一枚脱がせて、30分後にもう一度計り直すと確実です。
-
衣類・室温を調整しよう: 熱があるときは赤ちゃんの体から熱を逃がしてあげることが大切です。服は肌着1枚程度の薄着にし、汗をかいていたら着替えさせます。室温は暑すぎず寒すぎず、20~22℃前後を目安に保ちましょう。適宜換気して空気をこもらせないこともポイントです。また、発熱のタイミングによってケアを調整します。熱の上がり始めで手足が冷たく震えているときは体を温かく包み、熱が上がりきって顔が赤く手足も熱いときは薄着にして熱を逃がすようにしましょう。赤ちゃんの様子を見ながら、快適に過ごせる環境を整えてあげてくださいね。
-
こまめに水分補給をする: 発熱時は汗をかいたり体温上昇で脱水症状になりやすいもの。赤ちゃんの場合はまだ自分で水分をとれないので、母乳やミルクをいつもより頻回にあげて水分補給を心がけましょう。離乳食期の子で食欲がない場合は無理に固形物を与えず、白湯や乳幼児用イオン飲料(経口補水液など)で水分をとってもOKです。おしっこの量が極端に減っていないか(オムツが6時間以上乾いていないか)も確認しましょう。
-
安静に休ませ、必要に応じて体を冷やす: 赤ちゃんがぐったりしているときは、無理に遊ばせたりせず静かに休ませてあげましょう。眠れるようなら寝かせてあげてください。ただし、ずっと抱っこで揺らすより、少し頭を高くした状態で寝かせてあげるほうが呼吸が楽な場合もあります。咳込んで苦しそうなときは背中をさすってあげるなど、楽な姿勢を探ってみましょう。また、体を冷やすケアも状況に応じて行います。脇の下や首筋などに、タオルで包んだ保冷剤や冷たいタオルを当ててあげると熱を少し和らげることができます。額に冷えピタを貼るのも効果があります。ただし、赤ちゃんが嫌がる場合は無理に続けなくて大丈夫です。機嫌を見ながら取り入れてくださいね。
-
医師に相談済みなら解熱剤も使用: 小児科で解熱剤(坐薬やシロップなど)を処方されている場合や、明らかに高熱で辛そうな場合は、指示通りに解熱剤を使っても構いません。特に熱性けいれんを起こしたことがある子や、40℃近い高熱でしんどそうなときは遠慮せず使いましょう。ただし自己判断で市販の解熱剤(大人用の薬など)を与えるのは絶対にNGです。赤ちゃんに使って良い薬か分からない場合は、必ず小児科医に相談してください。
以上が家庭でできる基本的なケアです。ポイントは**「赤ちゃんの様子をよく観察すること」と「無理をさせないこと」です。熱がある間は機嫌が悪くなったり寝苦しそうですが、看病するパパママも休めるときに休んでくださいね。次に、「どんな状態になったら病院に行くべきか」**の目安を解説します。
受診の目安:病院に行くタイミングは?
「熱が出たらすぐ病院へ連れて行くべき?様子を見るべき?」と判断に迷うことも多いでしょう。基本的に赤ちゃんの機嫌が良く水分もとれていれば、半日~1日ほどおうちで様子を見ても大丈夫です。とはいえ、次のような場合には早めの受診を考えましょう。
月齢が低い場合
特に生後3か月未満の赤ちゃんは免疫力が低く重い症状に至りやすいので注意が必要です。生後3か月未満で37.5℃以上の熱が出たときは、夜間でも躊躇せず医師に相談してください。生後1か月未満ならなおさら早めに受診しましょう。
高熱が続く場合
発熱が丸3日以上続く場合や、解熱剤を使っても熱が下がらない場合は受診のサインです。単なる風邪でも乳幼児では肺炎に進展するケースもありますので、「長引いておかしいな」と感じたら診察を受けましょう。
いつもと様子が違う場合
熱以外に激しく泣いて機嫌が全く直らない、反対にぐったりして反応が鈍い、顔色が明らかに悪い、といった 「普段と違う」様子が見られたら注意。たとえば授乳や食事ができない・明らかに嫌がって飲まない、おしっこが極端に少ない(脱水の可能性)、発疹が出た、呼吸が苦しそう、などの症状があれば早めに医師に相談してください。
けいれん(ひきつけ)を起こした場合
熱性けいれんは乳幼児の約10%に起こると言われています。初めて熱性けいれんを起こしたときや、けいれんが5分以上続くとき、呼びかけても意識がはっきりしないときなどは至急119番で救急車を呼びましょう。けいれん自体は多くの場合数分で自然に治まり後遺症も残しませんが、初回は他の原因(てんかん等)との鑑別も必要です。発作中は体を横向きにして確保し、慌てず見守りましょう。救急隊に伝えるため、発作の様子をスマホで撮影できるとベストです。
上記のようなケース以外でも、「なんだか心配だな…」と感じるときは無理せず小児科に連絡・受診してOKです。特に赤ちゃんは症状の進み方が早いこともありますから、少しでも不安があれば遠慮なく専門家を頼ってくださいね。私たちせいせきこどもクリニックでも、お電話での相談や受診を随時受け付けています。
まとめ:落ち着いた対応で赤ちゃんの発熱を乗り切ろう
赤ちゃんの「初めての発熱」は、パパママにとってドキドキの体験です。しかし発熱自体は赤ちゃんが病気と戦っている証。過度に怖がる必要はありません。今回ご紹介した原因の知識やホームケアの方法、受診の目安を頭に入れておけば、いざという時も落ち着いて対応できるはずです。
大切なのは、赤ちゃんの様子をよく観察することとパパママが不安なときは早めに相談すること。赤ちゃんは小さな体で一生懸命ウイルスと闘っています。ママ・パパも深呼吸して、しっかり水分や休息を取らせてあげながらサポートしていきましょう。もちろん、少しでも「おかしいな」「心配だな」と思えば、いつでも私たち小児科医に頼ってくださいね。
発熱の峠を越えたら、きっと赤ちゃんはまた元気な笑顔を見せてくれるでしょう。ゆっくり休んで回復を待ちながら、焦らず見守ることも立派なケアです。今回の記事が少しでも皆さんの安心材料になれば幸いです。これからもせいせきこどもクリニックのブログで、育児中の皆さんに役立つ情報をお届けしていきます。一緒に子育ての不安を乗り越えていきましょうね!📖✨
🌸 せいせきこどもクリニックからのお知らせ
聖蹟桜ヶ丘駅近くの当院は、土曜・日曜とも午前/午後に一般外来・発熱外来・健診・予防接種・アレルギー外来を全て受診可能な多摩市で唯一のおすすめの小児科です。平日お忙しいご家庭や部活動などで平日の受診が難しいお子さまの選択肢としてぜひご利用ください。
📅診療時間のご案内
-
午前: 8:30~12:30(受付終了 12:15)
-
午後: 14:30~18:00(受付終了 17:45)
-
休診日: 火曜・祝日
※土日も診療を行っておりますので、平日お忙しい方もご利用いただけます。
📍アクセス
〒206-0002 東京都多摩市一ノ宮4-20-23 バモス聖蹟1階
京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」から徒歩約9分。提携駐車場がございますので、お子さま連れでも安心してご来院いただけます。