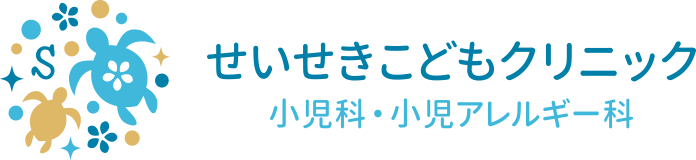目次
子育て中のパパママ、そしてこれから親になる皆さん、こんにちは!👋 日々の家事や育児、本当にお疲れ様です。そんな皆さんを応援するための大切な制度、「児童手当」について、今日はビッグニュースをお届けします。
児童手当は、家庭における生活の安定に寄与し、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的とした、国からの心強いサポートです。この児童手当が、令和6年10月から大きくパワーアップしたんです!✨ 内容がガラッと変わる部分もあるので、知らないと、もらえるはずの手当を見逃してしまうかも…?
この記事では、新しい児童手当の
-
「うちの子は何歳までもらえるの?」
-
「気になる金額はいくらになるの?」
-
「これまであった所得制限はどうなるの?」
-
「支給日はいつ?」
-
「手続きはどうすればいいの?」
といった疑問に、一つひとつ丁寧にお答えしていきます。特に、令和6年10月からの変更点を中心に、こども家庭庁の情報を元に分かりやすく解説しますので、ぜひ最後までチェックしてくださいね!
この制度変更は、子育て家庭への支援をより手厚くし、子どもたちが健やかに成長できる環境を社会全体で支えていこうという、国からの強いメッセージの表れと言えるでしょう。いくつかの重要な変更点が同時に実施されることからも、子育てにかかる経済的な負担を軽減し、安心して子どもを産み育てられる社会を目指すという、政府の明確な方針がうかがえます。しかし、どんなに素晴らしい制度も、その内容が皆さんに届かなければ意味がありません。この記事が、新しい児童手当の情報を正しく理解し、適切に活用するための一助となれば幸いです。
うちの子は何歳まで?👶➡️🧑 児童手当の対象年齢が拡大!(児童手当 何歳まで)
まず、最も大きな変更点の一つが、児童手当をもらえるお子さんの年齢です。
これまで、児童手当の支給対象は「中学校修了まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)」のお子さんでした。しかし、令和6年10月からは、この対象年齢が拡大され、なんと**「高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)」**のお子さんまで広がりました!🎓 こども家庭庁の資料でも、この支給期間の延長が明記されています。
「高校生年代」とは、具体的には18歳になって最初の3月31日を迎えるまでのお子さんを指します。つまり、高校を卒業する年齢まで、手当が継続して支給されるようになるのです。これは、高校進学やその後の準備など、教育費の負担が大きくなる時期の家計にとって、非常に大きな助けとなるでしょう。
この変更は、令和6年10月分の手当(多くの場合、最初の支払いは令和6年12月)から適用されました。原則として、手当の対象となるお子さん(こども家庭庁の定義では「児童」とは18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者)が日本国内に住んでいる場合に支給されますが、留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合には支給対象となることもあります。
高校生の時期は、学費だけでなく、塾や予備校、部活動、進学や就職の準備など、何かと出費がかさむものです。これまでは中学校卒業と同時に児童手当の支給が終了し、ちょうど教育費の負担が増すタイミングで支援が途切れてしまうという課題がありました。今回の対象年齢の拡大は、こうした高校生年代の子育てにかかる経済的な負担を継続的に支援するものであり、子どもたちが安心して学業に専念できる環境を整える上で重要な意味を持ちます。また、家計への負担が軽減されることで、より多くの子どもたちが希望する進路を選択しやすくなるなど、長期的に見れば、より質の高い教育を受けた人材育成にも繋がる可能性を秘めています。
気になる金額は?💰✨ 新しい児童手当の支給額をチェック!(児童手当 金額)
対象年齢が広がることが分かったところで、次に気になるのはやっぱり「いくらもらえるの?」という金額ですよね!😊 新しい児童手当の月額(お子さん一人あたり)は、以下のようになります。
【令和6年10月分からの児童手当月額】
| 年齢区分 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|
3歳未満 |
15,000円 |
30,000円 |
|
3歳以上~高校生年代(18歳年度末まで) |
10,000円 |
30,000円 |
表を見ていただくと分かる通り、特に注目なのが、第3子以降のお子さんの手当額がグーンとアップして、年齢に関わらず月額30,000円になる点です!👨👩👧👦 これまで、第3子以降の加算額は3歳から小学校修了前までは15,000円でしたが、これが3歳未満のお子さんと同じ30,000円に統一され、さらに高校生年代までその金額が維持されることになります。
「第3子」の数え方が変わります!カウント対象の兄姉が拡大!
そして、この「第3子以降」のカウント方法も、今回の改正で重要な変更点があります。こども家庭庁の資料によると、このカウント対象となる兄姉の年齢が、これまでの18歳年度末から22歳年度末まで延長されました。
具体的に言うと、これまでは主に18歳年度末までの子ども(高校生年代まで)を対象に第何子かをカウントしていました。しかし、令和6年10月からは、**「児童の兄姉等」として「18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子」**も、多子加算のカウント対象に含まれるようになったのです。
例えば、20歳の大学生のお子さん(親が学費などを仕送りしていて経済的な負担がある)がいて、次に10歳のお子さん、そして2歳のお子さんがいるご家庭の場合を考えてみましょう。
-
現行制度(~R6.9月分): 20歳のお子さんはカウント対象外。10歳のお子さんが第1子、2歳のお子さんが第2子。
-
新制度(R6.10月分~): 20歳のお子さん(経済的負担あり)もカウント対象になるため、10歳のお子さんが第2子、そして2歳のお子さんが第3子として扱われ、月額30,000円の支給対象となります。
これは、大学生など年長の子どもがいる多子世帯にとって、非常に大きなメリットと言えるでしょう。ただし、重要な注意点として、この「児童の兄姉等」をカウントに含めるには、親などがその兄姉等に対して監護に相当する世話をし、その生計費を負担している必要があります。そのため、18歳を超えて22歳年度末までの兄姉を第3子以降のカウントに含める場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」などの書類提出が必要になることがありますので、お住まいの市区町村にご確認ください。
この第3子以降への手厚い支援と、カウント対象となる兄姉の年齢拡大は、少子化対策として、より多くの子どもを持つ家庭を経済的に力強くサポートしようという国の明確な意図が込められています。特に大学進学などで教育費の負担が長期間にわたる現代において、年長の扶養家族がいる場合の負担を考慮したこの変更は、現実的な家計の状況に即した改善と言えるでしょう。これにより、経済的な理由で第3子以降の出産をためらっていた家庭にとって、少しでもハードルが下がる可能性があります。また、増額された手当は、子どもの教育資金や習い事、家族でのレジャーなど、子どもの成長や家族の生活の質を高めるための費用に充てられることが期待され、間接的に地域経済の活性化にもつながるかもしれません。
もう迷わない!児童手当の所得制限はどうなったの?🤔 (児童手当 所得制限)
これまで多くのご家庭を悩ませてきた児童手当の所得制限。これについても、令和6年10月分から大きな変更がありました!
ズバリ、児童手当の所得制限は、令和6年10月分から撤廃されました! 🎉
これまでは、養育者の所得に応じて、手当が満額支給される世帯、手当額が一律月額5,000円になる「特例給付」の対象となる世帯、そして所得が上限限度額を超えて支給対象外となる世帯がありました。しかし、今回の改正により、この所得による区分がなくなり、原則として全ての子育て世帯が、所得に関わらず満額の児童手当を受け取れるようになりますした。
「うちは所得制限で対象外だったから…」「特例給付だったから増額は関係ないかな…」と諦めていたご家庭も、これからは満額支給の対象となるのです。これは本当に大きなニュースですよね!
ただし、国の公式ウェブサイト(こども家庭庁など)では、情報更新のタイミングによって、まだ古い情報(所得制限に関する記述が残っていたり、撤廃が明記されていなかったりするケース)が掲載されている場合があるかもしれません。例えば、一部の資料では「所得制限に関する具体的な記載はない」、または「所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方については、制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要になる」といった記述が見られることもあります。しかし、複数の自治体の情報や報道、そしてこども家庭庁の最新の概要資料 を総合すると、「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)に基づく児童手当法の改正により、令和6年10月からは所得制限がなくなることが決定していますのでご安心ください。
なお、児童手当は、原則として父母等のうち、その家庭において生計を維持する程度の高い者(一般的には所得の高い方)が受給者となります。
所得制限の撤廃は、児童手当制度をよりシンプルで分かりやすいものにするだけでなく、子育て支援の公平性を高める上でも重要な一歩です。これまでは、所得がわずかに制限額を超えただけで手当が減額されたり、支給されなくなったりすることで、不公平感を感じる家庭も少なくありませんでした。また、所得を計算し、区分を判定する作業は、申請者にとっても自治体にとっても煩雑なものでした。所得制限がなくなることで、こうした事務的な負担も軽減されます。何よりも、「すべての子どもは社会の宝」という理念のもと、所得の多寡にかかわらず、子育てをするすべての家庭を社会全体で支えていくという、より普遍的な支援の形へと近づくことになります。これにより、これまで対象外だった中間所得層以上の家庭も新たに手当の恩恵を受けることになり、制度の対象者が大幅に拡大します。これは、子育て支援策の裾野を広げ、より多くの家庭に安心感を届けることに繋がるでしょう。
いつ振り込まれるの?🗓️ 新しい児童手当の支給日カレンダー (児童手当 支給日)
手当がいつ振り込まれるのか、しっかり把握しておきたいですよね!この児童手当 支給日についても、令和6年10月から変更がありました。
これまでの児童手当は、原則として年3回(2月、6月、10月)の支給でした。これが、令和6年10月からは**年6回(偶数月の2月、4月、6月、8月、10月、12月)**の支給に変わりました!🙌
それぞれの支払期には、その前月までの2ヶ月分がまとめて支給されます。
例えば、6月の支給日には、4月分と5月分の児童手当が振り込まれる、という形です。
そして、この制度改正後の最初の振り込みは、多くの自治体で令和6年12月に、10月分と11月分の手当が支給される予定となっています。具体的な振込日は市区町村によって若干異なる場合があるので、お住まいの自治体からの案内を確認してくださいね。
支給回数が年3回から年6回に増えることで、家計のキャッシュフロー管理がしやすくなるというメリットがあります。これまでは4ヶ月に一度のまとまった金額の振り込みでしたが、2ヶ月ごとになることで、よりコンスタントに手当を受け取れるようになります。これにより、毎月の食費や日用品、子どもの習い事の月謝など、定期的な支出計画が立てやすくなるでしょう。特に、一度に大きな金額が入るよりも、こまめに受け取る方が家計を管理しやすいと感じる方にとっては、歓迎すべき変更点です。また、次の支給までの期間が短くなることで、急な出費があった際の心理的な安心感にも繋がるかもしれません。
どうすればもらえるの?手続きカンタン解説📝
さて、これだけ内容が充実する児童手当、どうすればもらえるのでしょうか?手続きについて解説します。
初めて申請する方・新たに対象になる方
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したとき、そして今回の制度改正で新たに対象となる方(例えば、これまで所得制限で対象外だった方や、高校生年代のお子さんを養育している方など)は、お住まいの市区町村の窓口(またはオンライン)で**「認定請求書」**を提出する(申請する)必要があります。
【特に重要なポイント:制度改正で新たに申請が必要になる方へ】
今回の制度改正により、
-
高校生年代のお子さんを養育している方(現在中学生以下のお子さんの手当を既に受給している場合は、改めての手続きが不要な場合もあります)
-
これまで所得制限によって児童手当や特例給付の対象外だった方
といった方々は、新たに申請が必要になる場合があります。
これらの新たに申請が必要となる可能性のある方は、令和7年3月31日までに申請を行えば、令和6年10月分から遡って手当が支給されます! 🏃♀️💨 。この期限を過ぎてしまうと、原則として申請した月の翌月分からの支給となり、遡っての支給は受けられなくなってしまうので、忘れずに手続きをしましょう。
申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当は受け取れなくなるため、お子さんの出生や転入など、支給要件に該当したら速やかに申請することが大切です。
申請に必要なもの(一般的な例)
申請には、主に以下のようなものが必要となります。ただし、市区町村や個々の状況によって異なる場合があるため、必ず事前にお住まいの市区町村にご確認ください。
-
請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
-
請求者名義の金融機関の普通預金通帳またはキャッシュカード(手当の振込先)
-
請求者の健康保険証の写し(会社員などの被用者の場合)
-
その他、状況に応じて必要な書類(例:所得証明書、住民票、18歳を超えて22歳年度末までの兄姉に関する「監護相当・生計費の負担についての確認書」など)
公務員の方
公務員の方は、勤務先に申請が必要です。所属庁の指示に従って手続きを行ってください。
現況届について
以前は、毎年6月に児童手当を引き続き受けるための「現況届」の提出が必要でしたが、令和4年度からは原則として提出が不要になっています。これにより、多くのご家庭で手続きの負担が軽減されました。
ただし、以下のような一部の方は、引き続き現況届の提出が必要となる場合がありますので、お住まいの市区町村からの案内に注意してくださいね。
-
離婚協議中で配偶者と別居している方
-
配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
-
支給要件児童の戸籍がない方
-
施設等受給者の方
-
その他、市区町村から提出の案内があった方
制度改正に伴い、これまで対象外だった方が新たに対象となるため、この申請猶予期間(令和7年3月31日まで)と遡及支給の措置は非常に重要です。国や自治体も周知に努めていますが、情報が行き届かない可能性も考慮し、このような救済措置が設けられています。これにより、制度変更を知るのが遅れたり、すぐには申請手続きができなかったりした場合でも、不利益を被ることなく、新しい制度の恩恵を最大限に受けられるよう配慮されています。現況届が原則不要になったことも、子育て中の多忙な家庭にとっては大きな負担軽減です。ただし、例外的に提出が必要なケースもあるため、自分自身が該当するかどうかを市区町村からの通知などで確認することが大切です。
まとめ:パワーアップした児童手当を活用しよう!💪
令和6年10月からの児童手当は、
-
✅ 支給対象が高校生年代まで拡大
-
✅ 所得制限が撤廃
-
✅ 第3子以降は月額30,000円に増額(兄姉の年齢カウントも22歳年度末まで拡大)
-
✅ 支給回数が年6回(偶数月)に
と、子育て世帯にとって本当に心強い内容に大きく変わります!
ご自身が対象になるか、いつから、いくらもらえるのか、この記事を参考にぜひチェックしてみてくださいね。そして、新たに申請が必要な方は、忘れずに期限内(令和7年3月31日までなら令和6年10月分から遡及支給!)に手続きを行いましょう。
この新しい児童手当が、皆さんの子育てを少しでも力強くサポートするものになることを願っています。😊 子育ては大変なことも多いですが、こうした制度を上手に活用して、少しでも心穏やかに、そして楽しくお子さんとの毎日を過ごせるように、社会全体で応援しています!
【重要】令和6年10月からの児童手当改正ポイント早わかり表
最後に、今回の改正ポイントをまとめた表で、変更点を一目で確認しましょう!
| 項目 | 改正前(~令和6年9月分) | 改正後(令和6年10月分~) | 出典(主に改正後) |
| 項目 | 改正前(~令和6年9月分) | 改正後(令和6年10月分~) |
|---|---|---|
| 支給対象年齢 | 中学校修了まで(15歳年度末まで) | 高校生年代まで(18歳年度末まで) |
| 所得制限 | あり(所得に応じて特例給付または支給なし) | なし(撤廃) |
| 手当月額(第3子以降) | 3歳未満:15,000円<br>3歳~小学校修了まで:15,000円<br>中学生:10,000円 | 一律 30,000円 (0歳~高校生年代まで) |
| 第3子のカウント対象となる<br>兄姉等の年齢上限(扶養の場合) | 主に18歳年度末まで | 22歳年度末まで <br>(親等に経済的負担がある場合) |
| 支給回数 | 年3回(6月、10月、2月) | 年6回(偶数月:2,4,6,8,10,12月) |
この表で、変更点がスッキリ整理できたでしょうか? 新しい児童手当制度について、ご不明な点があれば、お住まいの市区町村の児童手当担当窓口にお問い合わせくださいね。
【参考文献】
* こども家庭庁「児童手当制度のご案内」 (https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai#hajime)
* こども家庭庁「児童手当制度が変わります!」(https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen)
* 内閣官房「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定) – 関連箇所
* こども家庭庁「児童手当Q&A」 (https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/qa/)
* こども家庭庁「もっと、子育て応援!児童手当 (「第3子以降」のカウント方法について)」