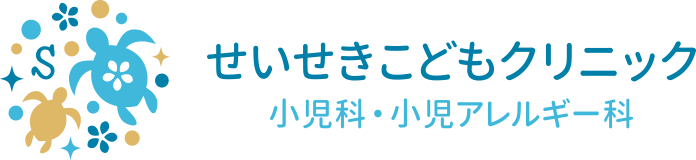目次
1. はじめに:赤ちゃんの便秘、ママは心配ですよね 😥
毎日赤ちゃんの様子を見ているママだからこそ、ちょっとした変化にも敏感になりますよね。「うちの子、最近うんちが出ていないかも…」「出すときに苦しそう…」なんてことがあると、「もしかして便秘なのかな?」「何か悪い病気だったらどうしよう…」と、心配でたまらなくなるのは当然のことです。初めての育児なら、なおさら不安に感じることも多いでしょう。
でも、安心してくださいね。赤ちゃんの便秘は、実は多くのママが経験する悩みのひとつなんです。
この記事では、そんなママたちの不安を少しでも軽くできるように、赤ちゃんの便秘について、小児科医も参考にしている資料や、多くのママたちが実際に検索して情報を得ているポイントをもとに、便秘のサインの見分け方から、お家でできる優しいケア方法、そして「こんな時は病院へ」という受診の目安まで、具体的でわかりやすい情報をお届けします。
大切なのは、ママが一人で抱え込まないこと。正しい知識を持って、落ち着いて対処することができれば、赤ちゃんの便秘の悩みもきっと乗り越えられます。一緒に赤ちゃんの便秘の悩みを解消していきましょう!💪
2. これって本当に便秘?赤ちゃんのうんちサインをチェック!✅
「うちの子、便秘かも?」と思っても、赤ちゃんのうんちは本当に個人差が大きいものです。飲んでいるもの(母乳かミルクか)、月齢、赤ちゃんの体質によって、うんちの回数も硬さも色も本当に様々!。例えば、母乳の赤ちゃんはうんちが緩めで回数が多い傾向があったり、ミルクの赤ちゃんは少し硬めで回数が少ないこともあります。毎日うんちが出なくても、赤ちゃん自身がご機嫌で、おっぱいやミルクをしっかり飲んでいれば、それはその子のペースということも多いんですよ😊。
では、どんな状態だと「便秘」を疑うべきなのでしょうか?
一般的に、1歳以上の幼児や学童では、排便回数が週に3回より少ない場合に便秘が考えられます。赤ちゃんの場合、この基準をそのまま当てはめるのは難しいこともありますが、多くの専門家は、1週間にうんちの回数が3回より少ない場合は、便秘を疑う一つのサインとしています。
ただ、回数だけでなく、うんちの状態や赤ちゃんの様子も大切なチェックポイントです。
赤ちゃんからの便秘のサイン 🤔
- うんちの回数が極端に少ない:例えば、新生児期を過ぎて4日以上うんちが出ない、または1週間に2回以下など、普段のその子のペースと比べて明らかに少ない場合。
- うんちが硬くてコロコロしている:まるでうさぎのフンのような、小さくて硬いぽろぽろしたうんちが出る🐇。
- 出すときにとても苦しそう、痛がって泣く😭:顔を真っ赤にしていきんでもなかなか出なかったり、排便時に痛くて泣いてしまう。
- お腹がカチカチに張っている:触ってみて、普段よりお腹が張って硬い感じがする。
- 食欲がない、または母乳・ミルクの飲みが悪い🤢:お腹が苦しくて、いつものように飲んでくれない。
- 排便後もスッキリせず、ぐずることが多い:うんちが出ても少量だったり、まだ苦しそうにしている。
- 肛門が切れて血がつくことがある🩸:硬いうんちを無理に出そうとして、肛門の周りが切れてしまうことがあります。
もしかして「ディスケジア」?
赤ちゃんがうんちを出すときに、顔を真っ赤にして力んで唸っているのに、出てくるうんちは意外と柔らかい…なんてこと、ありませんか?これは**「ディスケジア(乳児排便困難症)」**といって、赤ちゃんがまだ排便の時にいきむ力とおしりの筋肉を緩めるタイミングをうまくコントロールできないために起こるものです。お腹の筋肉に力を入れることと、肛門を開くという2つの動きを同時に行うのは、赤ちゃんにとってはまだ難しいんですね。
このディスケジアは、病的な便秘とは違い、成長ととも自然に上手になっていくことがほとんどなので、うんち自体が硬くなければ、通常は治療の必要はありません。ママは心配になってしまうかもしれませんが、これも成長の一過程と捉えて、優しく見守ってあげましょう。
大切なのは、うんちの回数だけでなく、うんちの硬さ、色、そして何よりも赤ちゃんの機嫌や食欲など、全体的な様子を観察することです。普段から赤ちゃんのうんちの状態を気にかけておくと、いざという時に「いつもと違う」という変化に気づきやすくなりますよ。
3. どうして?赤ちゃんの便秘、主な原因はこれ!🤔
赤ちゃんの便秘には、いくつかの原因が考えられます。主なものをみていきましょう。
-
哺乳不足 (Insufficient Milk/Formula Intake)
特に母乳育児のママは、赤ちゃんが実際にどれくらいの量を飲んでいるのか分かりにくいことがありますよね。母乳やミルクの量が足りていないと、うんちを作る材料そのものが少なくなり、結果としてうんちの回数が減ったり、便秘になったりすることがあります。赤ちゃんの体重が順調に増えているか、おしっこがちゃんと出ているか(1日に6回以上が目安)などをチェックしてみましょう。もし哺乳不足が心配な場合は、母乳外来や小児科で相談してみるのも良いでしょう。
-
離乳食の開始や内容 (Start or Content of Solid Foods)
離乳食が始まると、赤ちゃんの腸内環境は大きく変化します。新しい食べ物に慣れる過程で、一時的にうんちが出にくくなることがあります。特に、食物繊維のバランスが崩れたり、水分摂取量が相対的に減ったりすると便秘になりやすいです。例えば、お米やパン、いも類などのでんぷん質の多いものをたくさん食べると、うんちが硬くなる傾向があると言われています。バランスの良い食事が大切ですね。
-
水分不足 (Lack of Hydration)
赤ちゃんは大人よりも体内の水分量が多く、汗もかきやすいため、気づかないうちに水分不足になっていることがあります。特に汗をたくさんかく夏場や、暖房で空気が乾燥しがちな冬場は注意が必要です。基本的には、低月齢の赤ちゃんは母乳やミルクで十分な水分が摂れていますが、離乳食が進んだり、たくさん汗をかいた時などには、医師に相談の上で白湯や麦茶などで水分補給を試みることもあります。ただし、便秘だからという理由だけで、自己判断で赤ちゃんに白湯をたくさん与えることは、特に低月齢の場合は哺乳量が減ってしまう可能性もあるため、推奨されていません。まずはかかりつけ医に相談してみましょう。
-
腸の動きが未熟 (Immature Gut Motility)
赤ちゃんの消化器官はまだ発達途中です。腸のぜん動運動(うんちを押し出す動き)も大人ほど活発ではないため、うんちが腸の中に留まりやすく、水分が吸収されて硬くなり、便秘を引き起こすことがあります。
-
環境の変化やストレス (Environmental Changes or Stress)
これは少し月齢が進んだ赤ちゃんに見られることがありますが、生活リズムの乱れや、お引越し、旅行などの環境の変化が、一時的に便秘の原因になることもあります。
-
まれなケース:病気が隠れていることも (Rare Cases: Underlying Illness)
頻度は低いですが、ごくまれに、ヒルシュスプルング病や鎖肛といった生まれつきの腸や肛門の病気、または甲状腺機能低下症などの全身の病気が便秘の原因となっていることがあります。もし、生まれてから一度も(またはほとんど)うんちが出ない、お腹がパンパンに張って苦しそう、体重が全く増えない、緑色の嘔吐を繰り返す、といった特に心配な症状が見られる場合は、自己判断せずにすぐに小児科を受診してくださいね。
これらの原因が一つだけではなく、いくつか組み合わさって便秘を引き起こしていることもあります。赤ちゃんの様子をよく観察し、何が原因になっているのかを考えることが、適切なケアへの第一歩となります。
4. おうちでできる!愛情たっぷり💕便秘解消ケア
赤ちゃんの便秘に気づいたら、まずはお家でできる優しいケアを試してみましょう。ママの愛情のこもったケアは、赤ちゃんにとって何よりの安心感に繋がりますよ。
-
「の」の字マッサージ 🌀
これは昔からよく行われている便秘ケアの定番ですね。赤ちゃんを仰向けに寝かせて、ママの手のひら全体を使って、赤ちゃんのおへその周りを時計回りに「の」の字を書くように、優しくマッサージしてあげましょう。腸の動きに沿ってマッサージすることで、うんちが出やすくなる効果が期待できます✨。お風呂上がりやオムツ替えの時など、赤ちゃんがリラックスしているタイミングで行うのがおすすめです。ただし、食後すぐは避けましょうね。優しく、ゆっくりと、赤ちゃんとコミュニケーションを取りながら行うのがポイントです。
-
綿棒浣腸(肛門刺激)👉
これは、綿棒で肛門を優しく刺激して、排便を促す方法です。少し勇気がいるかもしれませんが、正しく行えば赤ちゃんへの負担も少なく、効果的なケアの一つです。
【綿棒浣腸のやり方】
- 赤ちゃんを仰向けに寝かせ、おむつ替えシートなどを下に敷きます。
- 綿棒の先端(綿球の部分)に、ベビーオイルやワセリンをたっぷり塗ります。滑りを良くするためです。特にワセリンのような少し粘度のあるものが、皮膚を保護しやすくおすすめです。大人用の綿棒の方が軸がしっかりしていて使いやすいという声もあります。
- 赤ちゃんの両足首を優しく持ち、膝を曲げてお腹の方へ近づけるようなM字型の体勢にします。
- オイルを塗った綿棒を、肛門にゆっくりと1~2cmほど(綿球が隠れる程度)挿入します。
- 挿入した綿棒を、肛門の内側をなぞるように、優しく「の」の字を描くようにくるくると15秒~1分ほど刺激します。
- 無理強いは絶対に禁物です!赤ちゃんが嫌がったり、痛がったりする様子が見られたら、すぐに中止してくださいね。 この綿棒刺激がクセになってしまうのでは?と心配するママもいるかもしれませんが、専門家の間では、適切に行う限り習慣性になることはほとんどないと考えられていますので、必要な時には試してみてください。数日うんちが出なくて苦しそうな時には、この方法で排便のきっかけを作ってあげると、スッキリすることもあります。
-
水分補給のコツ 💧
低月齢の赤ちゃんは基本的に母乳やミルクで水分は足りていますが、離乳食が始まっている赤ちゃんや、夏場などで汗をたくさんかいた時には、水分が不足しがちです。母乳やミルクに加えて、医師に相談の上で、白湯や赤ちゃん用の麦茶などを少しずつ与えてみるのも良いでしょう。ただし、前述の通り、便秘だからといって自己判断で水分を過剰に与えるのは避けましょう。
-
離乳食期なら:食事でできること 🥦🥕🍎
もし赤ちゃんが離乳食を始めているなら、食事内容を見直すことも便秘解消に繋がります。
- 積極的に摂りたいもの:
- プルーンやリンゴ、柑橘系の果汁(必ず薄めて、ごく少量から試しましょう)。
- プレーンヨーグルト(乳酸菌が腸内環境を整えるのを助けます)。
- 食物繊維が豊富な野菜(さつまいも🍠、かぼちゃ🎃、ほうれん草、ブロッコリーなど)、海藻類(わかめなど、細かく刻んで)、きのこ類(細かく刻んで)。
- 水分を多く含む果物(梨🍐、桃🍑など)。
- 摂りすぎに注意したいもの:
- バナナ🍌や牛乳🥛は、適量なら問題ありませんが、摂りすぎると逆にうんちを硬くしてしまうことがあると言われています。
- お米やパンなどの炭水化物も、偏りすぎるとうんちが硬くなる原因になることがあります。色々な食材をバランス良く食べさせてあげることが大切です。
- 積極的に摂りたいもの:
-
生活リズムと運動 🤸♀️
規則正しい生活は、腸の働きを整える基本です。また、体を動かすことも腸の刺激になります。まだ自分でたくさん動けない赤ちゃんでも、ママが赤ちゃんの足を持って自転車こぎのような運動をさせてあげたり、うつ伏せで遊ぶ時間(タミータイム)を増やしたりするのも、腸の動きを活発にするのに役立ちますよ。抱っこして軽く揺らしてあげるだけでも、腸への良い刺激になることがあります。
これらのケアは、すぐに劇的な効果が現れるわけではないかもしれませんが、続けることで赤ちゃんの腸内環境が整いやすくなります。何よりも、ママが優しく触れてケアをすることは、赤ちゃんにとって大きな安心感となり、心身のリラックスにも繋がります。焦らず、赤ちゃんのペースに合わせて試してみてくださいね。
5. こんなときは病院へ!受診の目安リスト 🏥
お家でのケアを色々試してみても、なかなか赤ちゃんの便秘が良くならない時や、次のような症状が見られる場合は、自己判断せずに一度小児科のお医者さんに相談しましょう。
迷ったら相談!🏥 病院受診のサイン
- 何日も(例:新生児期を過ぎて4日以上)うんちが出ていない。
- お家でのケア(マッサージ、綿棒浣腸、食事の見直しなど)を続けても、便秘が全く改善しない、またはむしろ悪化しているように感じる。
- 赤ちゃんが非常につらそうにしている、いつもと違って激しく泣き続ける、ぐったりしている。
- お腹がパンパンに張ってカチカチに硬い、触ると痛がって泣く。
- 嘔吐を繰り返す(特に、黄色や緑色の胆汁のようなものを吐く場合は、腸閉塞などの緊急性が高い病気の可能性もあるため、すぐに受診が必要です!)。
- うんちに血が混じる状態が続く、または血の量が多い(肛門が切れた少量の出血なら様子を見ることもありますが、心配な場合は相談しましょう)。
- 体重がなかなか増えない、または減ってきている。
- 機嫌が極端に悪く、何をしても泣き止まない、活気がない。
- そして何よりも、ママの直感で「何かおかしい」「いつもと違う」と強く感じる時。
ママの「何か変だな」という感覚は、とても大切なサインです。医学的な知識がなくても、毎日赤ちゃんと接しているママだからこそ気づけることがあります。リストに当てはまらなくても、心配なことがあれば遠慮なく医療機関を頼ってくださいね。早めに相談することで、ママの不安も軽くなり、赤ちゃんも適切なケアを受けることができます。
6. 病院ではどんなことをするの?ちょっと安心豆知識 🩺
「病院に行ったら、どんなことをされるんだろう…」と、ドキドキしてしまうママもいるかもしれませんね。でも大丈夫、お医者さんは赤ちゃんの便秘の専門家です。まずは安心して相談できるように、病院で一般的に行われることを少しご紹介します。
まず、お医者さんはママから詳しく赤ちゃんの様子を聞きます(問診といいます)。いつから便秘か、うんちの回数や硬さ、赤ちゃんの機嫌や食欲、試したケアなどを具体的に伝えられるようにしておくとスムーズです。この時、後述する「うんち日記」が役立ちますよ。
次に、お腹を触ったり聴診器をあてたりして、お腹の張り具合や腸の音などを確認します(触診・聴診)。場合によっては、肛門の様子を診たり、指で直腸の様子を確かめることもあります。
これらの診察で、特別な病気が疑われるような場合(例えば、お腹にしこりがある、肛門の形がおかしいなど)でなければ、レントゲン撮影や超音波検査などの詳しい検査をすぐに行うことは少ないです。
そして、診察の結果、治療が必要と判断された場合には、赤ちゃんにも使えるお薬が処方されることがあります。
- 糖類下剤:マルツエキス(麦芽糖)やラクツロースといったお薬は、腸の中で水分を集めてうんちを柔らかくする働きがあります。甘くて赤ちゃんも比較的飲みやすいため、よく使われます。
- 塩類下剤:酸化マグネシウムなども、うんちを柔らかくする効果が高いお薬です。幼児期以降でよく使われますが、赤ちゃんの状態によっては少量から試されることもあります。
- 刺激性下剤:ラキソベロン(ピコスルファートナトリウム)のようなお薬は、腸を直接刺激して動きを活発にしますが、赤ちゃんへの使用はより慎重に、医師の厳密な指示のもとで行われます。
- 浣腸:うんちが硬くてなかなか出ない場合には、病院でグリセリン浣腸などを行って、まず溜まったうんちを出す処置をすることもあります。市販の大人用浣腸薬を自己判断で赤ちゃんに使うのは、濃度や量が強すぎて危険なため絶対に避け、必ず医師の指示に従いましょう。
お薬の種類や量は、赤ちゃんの月齢、体重、便秘の程度などを総合的にみて、お医者さんが判断します。自己判断で量を増やしたり減らしたり、途中でやめてしまったりすると、かえって便秘が悪化したり、下痢になったりすることもあります。処方されたお薬は、必ず医師の指示通りに飲ませてあげることが、安全で効果的な治療のためにはとても大切です。
心配なことや疑問点は、遠慮なくお医者さんに質問して、納得して治療を進められるようにしましょうね。
7. 記録が大切!うんち日記をつけてみよう 📝
赤ちゃんの便秘が続いたり、病院にかかったりする場合には特に、「うんち日記」をつけておくことをおすすめします。日々のうんちの状態を記録しておくことは、便秘のパターンを客観的に把握したり、お医者さんに赤ちゃんの状態を正確に伝える上で、とても役立つんです。
何を記録するの?
難しく考える必要はありません。以下のようなことを、簡単にメモしておくだけでも十分です。
- 日付と時間(大体でOK)
- うんちの回数
- うんちの硬さ:コロコロ、硬い、普通、柔らかい、泥状、水様など(資料にあるようなスケールを参考にしても良いでしょう)
- うんちの色や量(いつもと違う場合は特に)
- 排便時の様子:スムーズに出たか、苦しそうだったか、泣いたか、いきんでいた時間など
- 機嫌や食欲
- 離乳食の内容(もし始めている場合)
- 試したケア:マッサージをした、綿棒浣腸をした、など
- 飲んでいる薬(もしあれば)
どうやって記録するの?
特別なノートを用意しなくても大丈夫。普段使っている手帳の隅っこや、カレンダー、スマートフォンのメモアプリなど、ママが続けやすい方法でOKです👍。大切なのは、毎日(またはうんちが出た時だけでも)記録を続けることです。
小児科の専門機関のウェブサイトなどでは、詳しい「排便日誌」のフォーマットがダウンロードできることもありますので、参考にしてみるのも良いでしょう。
この記録は、ママ自身の安心材料になることもあります。「あれ、何日出てないんだっけ?」と記憶が曖昧になることも防げますし、ケアの効果を客観的に見ることもできます。そして、お医者さんにとっても、この記録は診断や治療方針を決めるための非常に貴重な情報源となるのです。
8. おわりに:ママ、一人で悩まないでね 💖
赤ちゃんの便秘は、多くのママが一度は経験する悩みです。「うちの子だけどうして…」なんて思わないでくださいね。でも、正しい知識を持って、愛情のこもったケアをしてあげれば、きっと乗り越えられます!
一番大切なのは、ママが一人で全ての不安や責任を抱え込まないことです。赤ちゃんのことで心配なことがあったり、どうしていいか分からなくなったりしたら、遠慮なくかかりつけの小児科医や、地域の保健センターの保健師さんなどに相談してくださいね。専門家は、ママと赤ちゃんが安心して過ごせるようにサポートしてくれます。
この記事が、赤ちゃんの便秘で悩むあなたの不安を少しでも軽くし、赤ちゃんの毎日の「スッキリ快便💩」に繋がることを心から願っています。子育ては大変なことも多いけれど、赤ちゃんの笑顔は何よりの宝物。応援しています!😊