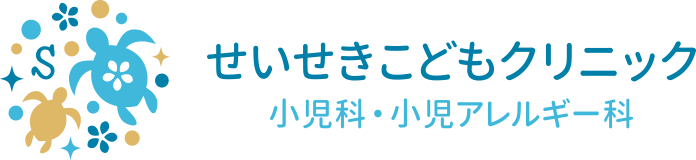目次
赤ちゃんのしゃっくり、”あるある”ですよね?😅
「うちの子、またしゃっくりしてる…」「これって大丈夫なのかな?」なんて、新米パパママは特にドキドキしちゃいますよね。でも、安心してください!赤ちゃんのしゃっくりは、実はとってもポピュラーなことなんです😊。多くの赤ちゃんが経験する、いわば成長過程の一コマのようなもの。実際、赤ちゃんはお腹の中にいる胎児の時から、しゃっくりをしているんですよ [1, 3, 4]。
この記事では、そんな赤ちゃんのしゃっくりについて、なぜ起こるのか、どうすれば優しくケアできるのか、そしてどんな時には少し注意が必要なのかを、分かりやすく解説していきます。この記事を読めば、赤ちゃんのしゃっくりに関するモヤモヤがスッキリ晴れて、今日から安心して対応できるようになりますよ。さあ、一緒に見ていきましょう!💪
どうしてしゃっくりが出るの?🤔 赤ちゃんのしゃっくりのメカニズムと主な原因
「ヒック、ヒック」と繰り返すしゃっくり。見ていると「苦しくないかな?」と心配になりますが、まずはその正体を知ることから始めましょう。
しゃっくりの正体は「横隔膜のビックリ運動」!
赤ちゃんの可愛らしい(でも時には心配な💦)しゃっくり音。その正体は、主に胸とお腹の間にある大きな筋肉のカーテンのような「横隔膜(おうかくまく)」が、何らかの刺激によってキュッと痙攣(けいれん)することで起こります [1, 3, 4]。この横隔膜の不随意な動き(自分の意思とは関係なく動いてしまうこと)によって、急激に空気が吸い込まれ、それと同時に喉の奥にある声帯(声門)もキュッと閉じてしまうため、「ヒック!」という特徴的な音が出るのです [1, 3]。医学的には「吃逆(きつぎゃく)」や「横隔膜痙攣」とも呼ばれ、筋肉がピクピクッと素早く不規則に動く「ミオクローヌス」の一つとされています [1]。
赤ちゃんは、体の様々な機能がまだ発達途中です。そのため、この横隔膜も大人に比べてデリケートで、ちょっとした刺激にも敏感に反応しやすいんですね👶。だから、大人よりも頻繁にしゃっくりが出やすいのです。
赤ちゃん特有!しゃっくりの主な引き金はコレ👇
では、具体的にどんなことが赤ちゃんの横隔膜を刺激し、しゃっくりを引き起こすのでしょうか?主な原因を見ていきましょう。
-
🍼 授乳との関係 (ミルクや母乳の飲み方):
一番多いのは、やはり毎日の授乳タイムに関連するものです🍼。
-
勢いよく飲む・一度にたくさん飲む: 赤ちゃんがゴクゴクと勢いよくミルクや母乳を飲んだり、一度にたくさん飲んだりすると、胃が急に膨らみます。この膨らんだ胃がすぐ上にある横隔膜を下から圧迫するように刺激してしまい、しゃっくりが出やすくなるのです [1, 3]。
-
空気の飲み込み: 授乳中に、ミルクや母乳と一緒に空気をたくさん飲み込んでしまうのも、よくある原因の一つです [3]。お腹に空気がたまると胃が膨らみやすくなり、ゲップと一緒にしゃっくりも出やすくなります。
-
飲み物の温度: ミルクが少し熱かったり、逆に冷たすぎたりすることも、胃を通して横隔膜への刺激となることがあります [1]。
-
-
🌬️ 体温の変化や不快感:
赤ちゃんの体は小さく、体温調節機能も未熟です。そのため、ちょっとした温度変化も刺激になりやすいのです。
-
体が冷える: 例えば、おしっこやウンチでおむつが濡れてヒヤッとした時や、お風呂上がりで体が冷えてしまった時など、体温が下がることでも横隔膜が刺激されてしゃっくりが出やすくなります [1, 3]。
-
室温の変化: 部屋の温度が急に変わったり、少し肌寒い環境だったりすることも影響することがあります。
-
-
🤔 その他 (まれなケースも知っておこう):
ほとんどの赤ちゃんのしゃっくりは、上記のような日常的な、そして生理的な原因によるものです。しかし、非常にまれではありますが、しゃっくりが何らかの体調不良のサインである可能性もゼロではありません。例えば、成人では脳や神経、呼吸器、消化器などの疾患が原因でしゃっくりが続くことが報告されています [1, 2]。ただし、これらは健康な赤ちゃんに当てはまることは極めて稀です。大切なのは、赤ちゃんのしゃっくりが一時的なもので、他に変わった様子がないかを見守ることです。ほとんどの場合は、日常的なケアで自然と治まるので心配いりませんよ👍。
これらの原因を理解することで、なぜしゃっくりが起こるのかが分かり、親御さんの不安も少し和らぐのではないでしょうか。多くは赤ちゃんならではの生理的な反応であり、成長とともに自然と減っていくものです。
うちの子だけ?心配いらない?😌 赤ちゃんのしゃっくりの特徴
「うちの子、しょっちゅうしゃっくりしてるけど大丈夫?」「他の子もこんなにするのかな?」と、心配になる親御さんは少なくありません。でも、結論から言うと、ほとんどの場合、赤ちゃんのしゃっくりは「大丈夫!」です😊 [1, 3, 4]。
実は、赤ちゃんがお母さんのお腹の中にいる胎児の時から、しゃっくりは始まっていることが知られています [1, 3, 4]。これは、生まれてからの呼吸の練習になっているのかもしれませんね。生まれてからも、消化器官や神経系など、体の様々な機能がまだ未熟な赤ちゃんは、大人よりもずっとしゃっくりが出やすいのです。その生理的な意義については、呼吸筋の発達に寄与しているのではないかという仮説もありますが、まだはっきりとは解明されていません [4]。
重要なのは、赤ちゃんのしゃっくりの多くは一時的で、**機能的なもの(病気ではないもの)**であるということです [1, 3]。つまり、何らかの病気が隠れているわけではなく、赤ちゃんの体が発達していく過程で見られる自然な現象の一つなのです。多くの場合、数分でおさまったり、授乳後にゲップをさせてあげるとケロッと止まったりします [1, 3]。特別な治療をしなくても、自然に止まることがほとんどなので、過度に心配する必要はありません。
この「しゃっくりは赤ちゃんにとって普通のこと」という認識は、親御さんの安心感につながります。しゃっくりを見るたびに不安になるのではなく、「ああ、また横隔膜が元気に動いているんだな」くらいに捉えられると、育児のストレスも少し軽減されるかもしれませんね。
これで安心!赤ちゃんのしゃっくり、優しい止め方&和らげ方リスト🤱
赤ちゃんのしゃっくりが始まると、早く止めてあげたいと思うのが親心ですよね。ここでは、赤ちゃんに負担をかけない優しい対処法をいくつかご紹介します。原因に合わせて試してみてくださいね。
-
💨 まずはゲップをしっかり!:
特に授乳後にしゃっくりが始まった場合は、飲み込んだ空気が原因かもしれません。授乳の後は、赤ちゃんを縦抱きにして背中を下から上へ優しくトントンしたり、さすり上げたりして、しっかりゲップを出させてあげましょう [1, 3]。お腹の空気が抜けることで胃から横隔膜への圧迫が減り、しゃっくりが止まりやすくなりますよ。
-
🍼 授乳のペースを見直そう:
一度にたくさん飲ませたり、赤ちゃんが急いでゴクゴク飲んだりすると、胃が急に膨らんだり、空気を飲み込みやすくなったりします。授乳は、途中で何度か休憩を挟みながら、少しずつゆっくりとしたペースであげるように心がけてみましょう [3]。
-
👶 抱っこの仕方を変えてみる:
少し体勢を変えるだけでも、横隔膜への刺激が変わり、しゃっくりが止まることがあります。一般的には、頭を少し高くした縦抱きがおすすめです [3]。
-
🤱 少量の母乳やミルクを:
ほんの少しだけ、母乳やミルクを飲ませてみるのも一つの方法です [3]。飲み込むという動作が、横隔膜の痙攣のリズムを変えるきっかけになることがあります。(ただし、生後6ヶ月未満の赤ちゃんに白湯などを与える場合は、量や頻度に注意し、基本的には母乳やミルクを優先しましょう。)
-
🌡️ 体を温めてあげる:
体が冷えてしゃっくりが出ているようなら、まずはおむつが濡れていないか確認しましょう。濡れていたら新しいものに替え、衣服を一枚多く着せたり、お腹のあたり(特にみぞおちのあたり [1])を優しく温めたタオルで包んであげたりするのも良いでしょう [1, 3]。赤ちゃんが快適な温度を保てるように気をつけてあげてください。
-
⏰ しばらく様子を見る:
実は、多くの場合、何もしなくても数分程度で自然に止まります [1, 3, 4]。焦らず、まずは赤ちゃんの様子を見守ってみましょう。しゃっくりをしていても、赤ちゃん自身が苦しそうでなければ、それほど心配はいりません。
これらの対処法は、しゃっくりの主な原因である「横隔膜への刺激」を和らげることを目的としています。どの方法が効果的かは赤ちゃんによっても異なりますので、いくつか試して、その子に合った方法を見つけてあげてくださいね。
ここで、状況に応じた対処法をまとめた表をご紹介します。ぜひ参考にしてください。
赤ちゃんのしゃっくり SOS!優しい対処法早見表
| こんな時 (原因のヒント) | 試してみて!優しいケア方法 | ポイント💡 |
|
授乳後によく出る、ゲップが少ないかも |
縦抱きで背中をトントン・さする |
しっかりゲップを出してあげよう [1, 3] |
|
ゴクゴク勢いよく飲んでいる、授乳中にむせることがある |
授乳を途中で区切る、ゆっくり飲ませる |
落ち着いて飲めるようにサポート [3] |
|
おむつが濡れている、手足が少し冷たい |
おむつ交換、衣服で調整、お腹や背中を温める |
赤ちゃんが快適な温度に [1, 3] |
|
特に原因が思い当たらない、でもしゃっくりが続く |
抱っこの体勢を変える、少量の母乳・ミルクを飲ませる、または、しばらく様子を見る |
自然に止まることも多いよ [3, 4] |
|
何をしてもすぐには止まらない、でも赤ちゃんはケロッとしている |
しばらく様子を見る |
赤ちゃんが苦しそうでなければ焦らないで [3, 4] |
この表はあくまで目安です。赤ちゃんの様子をよく観察しながら、優しく対応してあげることが大切です。
ちょっと待って!🚫 赤ちゃんのしゃっくりでやりがちなNG対応
赤ちゃんのしゃっくりを早く止めてあげたい一心で、ついやってしまいがちな行動の中には、実は赤ちゃんにとって好ましくないものもあります。ここでは、避けるべきNG対応について確認しておきましょう。
-
😱 ビックリさせて止めるのはNG!:
「ワッ!」と大きな音を出したりして驚かせるとしゃっくりが止まる、というのは昔から言われることがありますが、これは赤ちゃんには絶対にダメです! [3]。赤ちゃんを不必要に怖がらせてしまうだけで、しゃっくりを止める効果は期待できませんし、むしろ精神的なストレスを与えてしまう可能性があります。
-
🛌 うつ伏せ寝で止めようとしない:
しゃっくりを止めるために、赤ちゃんをうつ伏せにするのも避けましょう [3]。特に眠っている時にうつ伏せにすることは、乳幼児突然死症候群(SIDS)のリスクを高める可能性があるため、推奨されていません。
-
😭 無理に泣かせるのは…?:
「大泣きすると横隔膜の動きが変わってしゃっくりが止まる」と聞いたことがあるかもしれません [3]。確かに、結果的に止まることもありますが、赤ちゃんがしゃっくりで苦しそうにしているのでなければ、わざと泣かせる必要はありません。自然に止まるのを待つか、他の優しい方法を試してあげましょう。
-
🥄 大人と同じ対処法はしない:
大人がしゃっくりを止める時にするような、息を止めさせたり、コップの反対側から水を飲ませたり、何か特殊なものを飲ませたりする方法は、赤ちゃんには適していませんし、危険を伴うこともあります [3]。赤ちゃんの体は大人とは違うことを常に念頭に置きましょう。
これらのNG対応は、赤ちゃんの安全や心身の快適さを損なう可能性があります。しゃっくりはほとんどの場合、生理的な現象なので、焦らず、赤ちゃんに優しい方法で対応することが何よりも大切です。
こんな時は病院へGO!🏥 しゃっくりで受診を考える目安
ほとんどの赤ちゃんのしゃっくりは心配いりませんが、ごくまれに医療機関への相談が必要なケースもあります。「いつもと違うな」「なんだか様子がおかしいな」と感じたら、迷わず小児科医に相談しましょう。以下に、受診を考える目安をいくつか挙げます。
-
😫 呼吸が苦しそう・ゼーゼーしている:
しゃっくりと一緒に、呼吸が速い、息をするたびに胸がペコペコへこむ、息がゼーゼーヒューヒューいう、顔色や唇の色が悪い(青白い、土気色など)といった症状が見られる場合は、すぐに医療機関を受診してください [1, 2]。
-
🍼 おっぱいやミルクを全く飲めない・嘔吐を繰り返す:
しゃっくりがひどくて、いつまでもおっぱいやミルクを飲めない、または飲んでもすぐに吐いてしまうような状態が続く場合も相談が必要です [1]。栄養や水分が十分に摂れない可能性があります。
-
⏱️ 長時間止まらない・異常に頻繁:
しゃっくりが何時間もぶっ通しで続く、または、毎日何度も長時間にわたってしゃっくりを繰り返し、その間赤ちゃんが辛そうにしているなど、あまりにも頻度や持続時間が長いと感じる場合も、一度医師に相談してみましょう [1, 2, 3]。一般的な赤ちゃんのしゃっくりは、数分から長くても数十分程度で自然に止まることが多いです [1, 3, 4]。
-
🤒 他に気になる症状がある:
しゃっくり以外に、発熱がある、元気がなくぐったりしている、機嫌がずっと悪く泣きやまない、体重が増えないなど、普段と違う様子が見られる場合も、しゃっくりと関連がなくても、何らかの体調不良のサインかもしれません [1]。
これらはあくまで一般的な目安です。一番大切なのは、毎日赤ちゃんを見ているパパやママが「何かおかしいな」「いつもと違う」と直感的に感じることです。その直感はとても重要なので、少しでも不安なことがあれば、遠慮なくかかりつけの小児科医に相談してくださいね。それが一番大事なサインかもしれません👍。医師に相談することで、大きな安心感が得られることもあります。
まとめ:しゃっくりも成長のあかし😊 焦らず、愛情たっぷりで見守りましょう
赤ちゃんのしゃっくりについて、原因から対処法、注意点まで詳しく見てきましたが、いかがでしたか?多くの場合は心配いらないこと、そして優しい対処法があることを分かっていただけたでしょうか😊。
横隔膜がまだ未熟な赤ちゃんにとって、しゃっくりはある意味、体の機能が発達していく過程で見られる自然な姿の一つと言えるかもしれませんね。お腹の中にいた時から始まっているしゃっくりは、生まれてからも続く、赤ちゃん特有の生理現象です [1, 3, 4]。
授乳の仕方や室温の調整など、ちょっとした工夫でしゃっくりが出にくくなることもあります。そして、もししゃっくりが始まっても、慌てずにまずは赤ちゃんの様子を観察し、この記事で紹介したような優しい方法を試してみてください。
毎日たくさんの発見と、ちょっぴりの心配がある子育て。しゃっくりもその一つですが、この記事が少しでもパパママの安心につながり、赤ちゃんのしゃっくりと上手に付き合っていくための一助となれば嬉しいです。焦らず、赤ちゃんのペースに合わせて、愛情たっぷりで見守ってあげてくださいね💖。
参考文献
-
「新生児・乳児編 VI.全身 ■新生児期 240 しゃっくりはどうして出るのですか? どうすればよいですか?」.
-
岡本 宗一郎, 白井 由紀, 大嶋 健三郎. 「しゃっくりが止まらない」. 緩和ケア特集 息が苦しい、体がだるい・・・etc. “なんとなく気になる訴え”はこう見るべし! 症状アセスメントのポイント, 5.
-
三石 知左子. 「しゃっくりが止まらないのですが」. 特集 周産期の電話相談~テレフォントリアージ~| 新生児編 その他.
-
島 義雄.. 「しゃっくりはどうして出るのですか? どうすればよいですか?」. 新生児・乳児編 VI. 全身