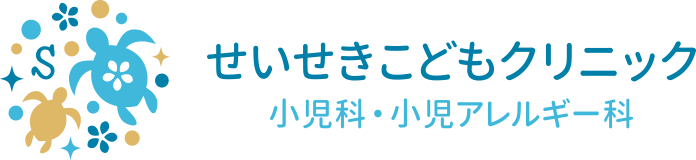目次
生まれた赤ちゃんも、生後2か月が近づくといよいよ予防接種デビューです。初めての予防接種となるママ・パパは不安や疑問がたくさんありますよね。「予防接種 スケジュール」はどう立てる?赤ちゃんにどんなワクチンを打つの?予防接種後に熱が出たらどうする?費用は医療費控除の対象になるの?・・・そんな初めての疑問に答えながら、東京都多摩地区を中心に、日本全国の保護者の方にも役立つ情報をまとめました。やさしい言葉と見出し・箇条書きで整理していますので、ぜひ安心して読み進めてくださいね。
予防接種はいつから始まるの?生後何ヶ月でデビュー?
赤ちゃんの予防接種は生後2か月からスタートします。生後1ヶ月健診を終えたら、かかりつけ小児科で2か月の誕生日以降の予防接種予約を取りましょう。例えば4月25日生まれの赤ちゃんなら6月25日頃から開始するイメージです。早めに予約を入れておけば、生後2か月になった時にスムーズに受け始められます。
なぜ生後2か月からなのでしょうか? 実は、赤ちゃんはお母さんからもらった病気への免疫が時間とともに薄れていきます。また乳児期は免疫機能が未発達で、病気にかかると重症化しやすいのです。例えば百日ぜきの抗体は生後まもなく低下し、**麻しん(はしか)**の抗体も生後6か月以降には失われてしまいます。そのため日本では、生後2か月になったらできるだけ早く予防接種を始め、重症化しやすい感染症にかかる前に免疫をつけておくことが大切とされています。
生後6か月までに受けるワクチンは定期接種だけでも4種類(10回以上)にもなります。 必要な回数を6か月までに完了させるには計画的な接種が必要です。1本ずつ別の日に打っているとスケジュールが間に合わなくなるおそれもあるため、後述する同時接種もうまく活用しましょう。特に5種混合、小児肺炎球菌、ロタウイルス、B型肝炎などは生後6か月までに必要回数を済ませることが推奨されています。
なお、多くの自治体では赤ちゃん誕生後、母子健康手帳と一緒に予防接種の案内や予診票のセットを配布します。東京都多摩地域でも、例えば立川市では「生まれた月の翌月末」に定期予防接種の案内一式が届く仕組みです。お住まいの地域の案内に従い、計画的に進めてくださいね。
ワクチンの種類と役割 ~ 定期接種と任意接種って?
赤ちゃんに受けさせるワクチンには**「定期接種」と「任意接種」**の2種類があります。それぞれ簡単に違いと役割を押さえておきましょう。
定期接種
予防接種法という法律に基づき、市区町村が公費(無料もしくは一部助成)で行うワクチンです。いわゆる「必須」の予防接種で、決められた時期に受けることで料金はかかりません。乳幼児期の定期接種には、小児用肺炎球菌(肺炎・髄膜炎の予防)、五種混合ワクチン(DPT-IPV-Hib;ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブの予防)、B型肝炎(肝炎ウイルスの予防)、BCG(結核の予防)、MR(麻しん風しん混合)、水痘(水ぼうそう)などがあります。これらは乳幼児がかかると重症化しやすい病気や流行性の高い病気で、社会全体で予防する意義も大きいものです。定期接種は赤ちゃんを病気から守り、流行を防ぐため国が特に重要と位置付けたワクチンと言えます。標準的な接種時期に受け忘れないよう、母子手帳のスケジュールを確認しながら計画しましょう。
任意接種
法律上の「定期」に含まれないワクチンで、接種は保護者の任意判断に委ねられます。ただし「任意」とはいえ、赤ちゃんを病気から守るため医師が接種を勧めるものも多くあります。費用は原則自己負担ですが、自治体によっては助成金制度がある場合もあります。代表的な任意接種には、ロタウイルスワクチン(乳児の重症胃腸炎を予防)、おたふくかぜ(ムンプス)ワクチン(流行性耳下腺炎の予防)、インフルエンザワクチン(季節性インフルエンザの予防)などがあります。例えば、おたふくかぜワクチンは1歳以上で接種するのが望ましく、乳幼児期になるべく受けておきたい任意接種です。またインフルエンザワクチンは生後6か月以降から毎年接種できます(1歳未満では効果が十分出にくいと言われますが、重症化予防のため接種可能です)。任意接種は有料とはいえ、赤ちゃんの将来の健康を守るために受けておく価値の高いワクチンが含まれます。費用負担とのバランスを考えつつ、かかりつけ医とも相談して検討してみましょう。なお任意接種の費用については後述の「医療費控除」の項で解説します。
赤ちゃんの予防接種スケジュール【カレンダー表】
初めてだと**「予防接種 スケジュール」をどう立てればいいか悩みますよね。ここでは標準的な赤ちゃんの予防接種スケジュール**を、生後順にカレンダー形式でまとめました。同時接種を前提に効率よく進めたモデルケースです。一覧表で全体像をつかんでおきましょう。
| 月齢・年齢 | 定期接種(公費) 対象疾患 | 任意接種(自費) 対象疾患 |
|---|---|---|
| 生後2か月 | 小児用肺炎球菌①(肺炎・髄膜炎)、五種混合①(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ)、B型肝炎①(肝炎)、ロタウイルス① 経口 | |
| 生後3〜4か月 | 小児用肺炎球菌②、五種混合②、B型肝炎②、ロタウイルス②(※2回目で完了のワクチンもあります) | |
| 生後5〜6か月 | 小児用肺炎球菌③、五種混合③、BCG(結核予防)、ロタウイルス③(※5価ワクチンの場合) | |
| 生後6か月以降 | ※B型肝炎③(生後7〜8か月頃までに完了) | インフルエンザ(冬季に応じ接種、6か月~) |
| 1歳の誕生日(12か月) | MR(麻しん風しん)①、水痘(水ぼうそう)① | おたふくかぜ①(ムンプス) |
| 1歳~1歳半頃 | ヒブ④(追加)、小児用肺炎球菌④(追加)、四種混合④(追加) | (おたふくかぜ②)※検討 |
| 1歳3か月~1歳6か月 | 水痘②(2回目) | (—) |
補足
上記は一般的なスケジュールです。赤ちゃんの体調や病院の方針により接種時期が前後する場合があります。また、ロタウイルスワクチンは初回接種の年齢制限があり、生後14週6日(約3か月半)までに開始する必要があります(ワクチンの種類によって完了時期も生後24週~32週までと制限あり)。医師と相談のうえ適切なタイミングで受けましょう。
表を見て「こんなにたくさん!大変そう…」と驚いたかもしれませんね。しかしご安心ください。同時接種を活用すれば、1度の通院で上記のように3~4種類まとめて受けることも可能です。実際、海外では生後2か月の赤ちゃんに6種類のワクチンを同時に接種するほどで、日本でも安全性が確認され推奨されています。小児科の先生と相談しながら、無理のないスケジュールで計画しましょう。
⇒ 1歳半以降のスケジュール: 乳幼児期の定期接種は1歳~1歳半でいったん区切りとなりますが、その後も追加接種や幼児期以降のワクチンがあります。代表的なものは日本脳炎ワクチン(1期初回は3歳頃×2回、1期追加は4歳頃、2期は9~12歳で1回)、MR2期(年長児の頃に1回)、小学校高学年で**二種混合(DT)や子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)**などです。これらについても就学前健診や学校から案内がありますので、適宜受け漏れのないようにしましょう。特にHPVワクチンは2022年から積極的勧奨が再開され、小学校6年生~高校1年相当の女子が定期接種の対象です(2023年からは男性への接種も開始)。幼児期を過ぎても、引き続きお子さんの予防接種の機会をチェックしてくださいね。
予防接種後の症状は?熱が出たらどうする?【副反応への対処】
初めての予防接種だと、赤ちゃんにどんな反応が出るか心配ですよね。一般的に予防接種後は軽い副反応が出ることがありますが、多くは心配のないものです。ここでは接種後に出やすい症状とケアの仕方について解説します。
接種直後の様子
病院でワクチンを打った後、15~30分ほど待合室で様子を見るよう指示されます。これは、まれに起こる急激なアレルギー反応(アナフィラキシー)がないか確認するためです。ほとんどの赤ちゃんは問題なく過ごせますが、顔色が悪い、激しく泣いてぐったりするなど異変を感じたらすぐ医療者に伝えましょう。
よくある副反応
接種した場所(腕や太もも)が腫れたり赤くなったりすることがあります。これはワクチンに対する免疫反応で、2~3日で治まります。入浴は当日から可能ですが、注射した部位を強くこすらないようにしましょう。また機嫌がふだんよりぐずる、一時的に食欲が落ちる、眠りがちになるといった様子が見られることもあります。これらも赤ちゃんの体がワクチンに慣れていく過程で見られる軽い反応です。普段通りの生活で問題ありませんが、赤ちゃんがぐずったら抱っこしてあやす、いつもよりこまめに水分補給させるなどして様子を見てあげてください。
発熱
予防接種後に熱が出ることも珍しくありません。多くの場合、接種した当日~翌日にかけて体温が上がりますが、その熱は1日程度で落ち着くことがほとんどです。 赤ちゃんが熱を出しても、母乳やミルクを普段通り飲めていて機嫌もそこそこ良く眠れているようなら、自宅で様子を見守って大丈夫です。無理に厚着をさせず室温を調整して、汗をかいたら着替えさせるなど体を楽にしてあげましょう。一方で、38℃を超える発熱が続く場合や、水分もとれないほどぐったりしている、泣き声が弱々しい・異常に機嫌が悪い、夜も泣いて眠れない、といったいつもと違う様子がある場合は早めに小児科に相談してください。 特に生後3ヶ月未満の赤ちゃんで38℃以上の発熱が見られた場合は必ず受診し、医師からの指示を仰ぎましょう。
その他まれな副反応
ごくまれに重いアレルギー反応(じんましん、呼吸困難など)やけいれん、**高熱(40℃以上)**などの症状が出ることがあります。これらは頻度こそ非常に低いものの、万一起きた場合は迅速な対応が必要です。接種後1週間程度は赤ちゃんの体調に注意し、明らかにおかしい症状があればすぐ医療機関で受診してください。予防接種が原因で重篤な健康被害が生じた場合、公費による救済制度(予防接種健康被害救済制度)があることも覚えておきましょう。
豆知識
予防接種の日、赤ちゃんはお風呂に入れる?
基本的に入浴は当日から可能です。予防接種を受けた日は「お風呂NG」と思われがちですが、注射した部位を清潔に保つためにも問題ありません。ただし、注射後に熱が出ている場合やぐずって機嫌が悪い場合は無理に入れず、体をやさしく拭いてあげる程度でも大丈夫です。
予防接種の費用と医療費控除について
赤ちゃんの予防接種、特に任意接種は家計的にも負担が気になるところですね。ここでは予防接種にかかる費用と、公的な費用補助や税制上のポイントについて説明します。
定期接種の費用
前述のとおり定期接種は公費負担で行われるため、対象年齢内であれば基本的に無料で受けられます。自治体から配布される予診票やクーポン券を持参し指定の医療機関で接種すれば、費用は発生しません(窓口で「〇円です」と請求されることもないはずです)。ただし接種を受けられる期間が決まっているものが多いので、期限を過ぎて任意接種扱い(自己負担)にならないよう注意しましょう。
任意接種の費用
任意接種は自己負担が基本で、料金はワクチンの種類や医療機関によって異なります。おおよその目安として、ロタウイルスワクチンは1回あたり1~1.5万円程度(種類によって2回または3回接種)、おたふくかぜワクチンは5,000円前後、インフルエンザワクチンは1回3,000~4,000円程度が多いようです。兄弟がいると人数分かかるのでまとまった負担になりますが、自治体によっては任意接種費用の助成制度を設けている場合もあります。 たとえば自治体によってはおたふくかぜやロタウイルスの予防接種券を配布し、数千円の助成をしているケースがあります。お住まいの地域の制度を市区町村のホームページ等で確認してみましょう。
医療費控除の対象になる?
自費で受けた予防接種の費用が医療費控除で税金の還付対象になれば嬉しいですが、残念ながら予防接種の費用は医療費控除の対象にはなりません。 税法上、病気の治療ではなく予防のための費用は「医療費」とみなされない決まりになっているためです。したがって、たとえばインフルエンザワクチン代や任意接種の費用は年間医療費の控除額に入れることはできません。
ワンポイント補足
近年、自己治療(セルフメディケーション)を促進するためのセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)という制度があります。この制度では、一定の条件(健康診断を受けている等)のもとで市販薬購入費を年額12,000円超えた分について控除できますが、その「一定の取組」の条件を満たす一例として予防接種の実施も挙げられています。つまり予防接種を受けることでセルフメディケーション税制を利用する資格要件は満たせるものの、ワクチンそのものの費用が控除されるわけではない点に注意してください。いずれにせよ、通常の医療費控除では予防接種代は控除対象外ですので、「予防接種の費用を少しでも減らしたい」という場合は前述の自治体助成などを積極的に活用すると良いでしょう。
初めての予防接種に向けて親が準備すべきこと
初めての予防接種の日を安心して迎えるために、ママ・パパが事前に準備しておきたいことをチェックリスト形式でまとめます。当日の持ち物や赤ちゃんの体調管理、スムーズに受けるコツなど、ぜひ参考にしてください。
持ち物のチェック
予防接種当日は予診票(接種券)と母子健康手帳を必ず持参しましょう。予診票は事前に記入を済ませ、当日スムーズに提出できるようにしておきます。そのほか、健康保険証や自治体発行の乳幼児医療証(医療費助成の受給者証)も念のため持って行きます。万一当日病院で診察が必要になった場合や、次回予約の登録などで必要になる場合があります。
授乳・食事のタイミング
接種時に赤ちゃんが空腹で泣いてしまわないよう、授乳や離乳食は病院へ出発する30分前までに済ませておきましょう。 特に、ロタウイルスワクチンのように経口で飲むワクチンを受ける場合は、げっぷや嘔吐でワクチンを吐き出さないよう接種1時間前までには授乳を終えておくことが望ましいです。お腹が満たされていれば赤ちゃんもご機嫌で受けやすくなります。
当日の健康チェック(体温・体調)
接種当日の朝は赤ちゃんの体温を測り、平熱か確認します。一般的に37.5℃以上の発熱がある場合は接種を延期するのが安全です。鼻水や咳など軽い風邪症状程度なら受けられる場合もありますが、自己判断せず病院に相談しましょう。予診票の問診欄にも当日の体調を書く欄があるので、少しでも気になる症状があれば事前に記入し、受付や予診時に伝えてください。「昨日まで便秘気味だった」「昨夜少し夜泣きした」等、ちょっとしたことでもOKです。医師が総合的に判断して接種可否を決めてくれます。
時間に余裕をもって行動
予約時間に遅れないよう、早めに家を出発しましょう。赤ちゃん連れだと、出かける直前におむつ替えや授乳が必要になったり、移動中にぐずって予定通り進まなかったりと何かと時間がかかります。また電車やバスの遅延が発生することもあります。接種会場(病院)には予約時間の15分前には到着するつもりで、時間に余裕をみておくと安心です。
服装の工夫
当日は赤ちゃんも親も脱ぎ着しやすい服装で行きましょう。赤ちゃんの場合、前開きのロンパースや肌着だと診察や接種がしやすいです。おすわり期以降の子であれば上下分かれた服(Tシャツ&ズボンなど)でもOKですが、腕や太ももに注射をするのでサッとまくれる服が良いでしょう。寒い時期でも厚着のしすぎは避け、温度調節しやすい上着やおくるみを活用してください。ママ・パパも抱っこや着替えの対応がしやすいよう、動きやすい服(パンツスタイルなど)がおすすめです。荷物が多くなりがちなので、両手が空くリュックで行くと移動も楽ですよ。
予約時間と機嫌対策
赤ちゃんが機嫌の良い時間帯を見計らって予約を入れるのもポイントです。普段から赤ちゃんの生活リズムを観察し、しっかりお昼寝した後やお腹が満たされている時間帯を選ぶと良いでしょう。「眠い」「空腹」のタイミングだと待ち時間にどうしてもぐずりやすくなります。また、病院で待つ間に飽きてしまったり泣き出したりした時のために、お気に入りのおもちゃや絵本をバッグに入れておきましょう。音の出ないガラガラや小さなぬいぐるみなどがあると、注意をそらしてあやすのに役立ちます。場合によってはスマホでいつも見せている動画や音楽を流すなども効果的です(周囲の迷惑にならない範囲で活用してくださいね)。
最後に、当日は保護者もリラックスして臨むことが大切です。赤ちゃんはママ・パパの緊張を敏感に感じ取ります。深呼吸して笑顔でいれば、赤ちゃんも安心してくれるでしょう。接種後は「よくがんばったね!」とたくさん褒めてあげてください。必要なら授乳やミルクで赤ちゃんを落ち着かせてから帰宅しましょう。
まとめ:予防接種を味方につけて、赤ちゃんの健やかな成長を守ろう
初めての赤ちゃんの予防接種は、不安も多いですが正しい知識と準備があれば怖がる必要はありません。予防接種は赤ちゃんを感染症から守る大切な盾です。スケジュールに沿って計画的に受けていけば、赤ちゃんは様々な病気に対する強い免疫を獲得していきます。東京都多摩地区をはじめ日本全国どこにいても、自治体や医療機関のサポートを受けながら進められますので安心してくださいね。
ママ・パパにとっては慣れない手続きや通院で大変に感じるかもしれませんが、成長するにつれてきっと「受けておいて良かった」と実感できるはずです。副反応への対処法やスケジュール管理のコツも押さえつつ、赤ちゃんの健やかな成長をみんなで見守っていきましょう。予防接種は赤ちゃんへの最初のプレゼントとも言えます。ぜひ前向きな気持ちで取り組んでくださいね。私たち先輩ママ・パパも応援しています!
🌸 せいせきこどもクリニックからのお知らせ
聖蹟桜ヶ丘駅近くの当院は、土曜・日曜とも午前/午後に一般外来・発熱外来・健診・予防接種・アレルギー外来を全て受診可能な多摩市で唯一のおすすめの小児科です。平日お忙しいご家庭や部活動などで平日の受診が難しいお子さまの選択肢としてぜひご利用ください。
参考文献・情報源
小児科専門サイト「Know VPD!」, 東京都保健医療局資料, 予防接種に関する厚生労働省・自治体情報, ベネッセ「たまひよ」育児情報, 楽天カード社「医療費控除」解説, 他. これらの情報をもとに作成しました。予防接種に関する最新の詳細はお住まいの自治体やかかりつけ医にご確認ください。赤ちゃんの健やかな成長をお祈りしています!